役員一覧
理事紹介
一般社団法人聴診データ研究会 の理事を紹介します。

代表理事 目々澤 肇
医療法人社団茜遥会
目々澤醫院 院長
医学博士、Ph.D.
日本頭痛学会 評議員・専門医
日本脳卒中学会・日本老年精神医学会 専門医
日本医師会 認定産業医
【専門分野】
脳卒中、頭痛、認知症
【略歴】
1933年に開設された目々澤醫院(東京都江戸川区)の第3代目院長。1981年に獨協医科大学医学部を卒業。スウェーデン・ルンド大学医学部実験脳研究所への留学経験も有する。東京都医師会では、地域包括ケアシステムの実現に必要なICTネットワーク構築の実現に努めているほか、医学生への医師会活動の啓発も行っている。
-
1981年 獨協医科大学医学部卒業
-
1987年 日本医科大学 医学博士取得
-
1988-90年 スウェーデン・ルンド大学医学部実験脳研究所留学 1993年 スウェーデン・ルンド大学医学部 Ph.D.取得
-
1993-97年 日本医科大学付属第一病院内科 医局長
-
1994-98年 日本医科大学内科学第二講座 講師
-
1998-99年 日本医科大学北総病院脳神経センター 副所長
-
1999年 日本医科大学内科学第二講座 兼任講師、現非常勤講師 1999年 医療法人社団茜遥会目々澤醫院 院長

理事 小林 泰之
聖マリアンナ医科大学
デジタルヘルス共創センター副センター長
大学病院画像センター 副センター長、医療情報処理技術応用研究分野大学院教授、大学病院放射線科顧問医
【専門/担当分野】
#1.画像診断(主に循環器領域)、Advanced CT/MRI Imaging、画像処理技術、画像情報システム(PACS/RIS)
#2.医療情報、医療におけるAI/ICT活用
【略歴】
-
1998年度 – 1999年度: 自治医科大学, 医学部, 助手
-
1999年度: 自治医科大学, 医学部, 助教授
-
2001年度 – 2002年度: 自治医科大学, 医学部, 助手
-
2013年度 – 2014年度: 聖マリアンナ医科大学, 医学部, 講師
-
2015年度 – 2016年度: 聖マリアンナ医科大学, 医学部, 教授
-
2019年度: 聖マリアンナ医科大学, 医学研究科, 教授
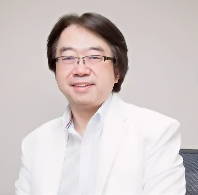
理事 宗田 聡
産婦人科医・産業医
筑波大学卒業。筑波大学医学部産婦人科講師、米国ボストンNew England Medical Center(NEMC)留学。帰国後、茨城県周産期センター長を経て、現在は広尾レディース院長。
【非常勤】
東京慈恵会医科大学産婦人科、筑波大学大学院人間総合科学研究科、 筑波大学医学医療系遺伝医学、首都大学東京健康福祉学部看護学科、 茨城県立医療大学客員教授
【専門医等】
日本産科婦人科学会認定医、臨床遺伝学認定医・指導医 日本医師会認定産業医、 産科医療補償制度原因分析委員会 委員 日本周産期メンタルヘルス学会評議員、日本産婦人科医会先天異常委員会委員 日本産科婦人科遺伝診療学会評議員、米国人類遺伝学会上級会員( (FACMG)
【所属学会】
日本産科婦人科学会、日本周産期メンタルヘルス学会、日本人類遺伝学会 米国人類遺伝学会(ASHG)、国際出生前診断学会(ISPD) など
【メッセージ】
新しく設立される聴診データ研究会の理事をさせていただくことになりました。医療界もこの20年の間に劇的にハードの改革が進み、自分が医者になったばかりの30年前までは、X線(レントゲン)写真、MRIフィルム等をシャウカステンといって蛍光灯等を備えた板上で病気の確認をしていました。 現在では、デジタル情報化によりフィルムレス運用が進み、モニター画面上で患者さんと共有しながら確認できるようになっています。画像同様に音声もデータ化により医師一人が心臓や呼吸の音を聴く時代から、共有できる時代へと変われます。さらに音のデーター化と解析により、これまで知り得なかった新しい知見がみつかる可能性があります。産科領域でも、お母さんのお腹の中の赤ちゃんの心臓の音を単に聴く時代から、それを継続的に記録することで、劇的に赤ちゃんの健康度をあげました。今後、この研究会で得られた聴診データにより病気の予防や早期発見につながることを期待しています。

理事 留目 真伸
株式会社SUNDRED 代表取締役
【略歴】
早稲田大学政治経済学部卒業。総合商社、戦略コンサルティング、外資系 IT、日系製造業等において要職を歴任。
レノボ・ジャパン株式会社、NEC パーソナルコンピュータ株式会社 元代表取締役社長。
株式会社資生堂 元チーフストラテジーオフィサー。
大企業のマネジメント経験、数々の新規事業の立ち上げ、スタートアップの経営を通じ、個社を超えて社会起点の目的を実現するソリューションの全体像を共創する仕組みが必要であると強く認識し、2019年7月よりSUNDREDにて「新産業共創スタジオ」を始動。